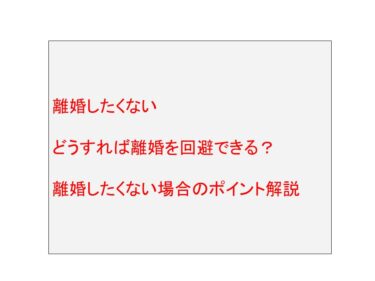最終更新日:2022年4月21日
1 はじめに
夫婦が別居をする際、児童手当の扱いが問題となることがあります。
夫婦が同居している期間は、子どもの生計を維持する者として、夫が児童手当を受給することが一般的です。
この状況のもと、妻が子どもを連れて別居をすると、別居後も夫が児童手当を受給し続ける状態が発生することがあります。
別居後、すぐに児童手当の受給者を妻に変更できればよいのですが、実際には、夫が児童手当を受給し続けてしまうことがよく起こります。
この場合、妻としては、「本来ならば私が受給する児童手当なのだから、別居後に支給された分は私に返してほしい」と望むことでしょう。
では、別居後に夫が受給した児童手当について、妻に返還するよう請求することはできるのでしょうか?
※本記事では、「夫に対し児童手当の返還を求める」という一般的な事例を前提に解説をいたします。ただ、夫と妻の立場が逆であっても結論は同じです。
「妻が児童手当の受給者となっており、夫が子どもを連れて別居をした」という事案では、夫と妻の立場を入れ替えて本記事をお読みください。
2 児童手当の受給資格は誰にあるのか
前提として、そもそも児童手当の受給資格は誰にあるのかを解説いたします。
児童手当の受給資格は、「児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父または母」にあります(児童手当法4条1項1号)。
そして、夫婦が別居した場合は、「父と母のいずれか一方が児童と同居する場合は、同居する親によって監護され、かつ、生計を同じくするものとみます」と定められ(児童手当法4条4項)、子どもと同居する側に受給資格があることになります。
上記の点については別記事(「別居中の児童手当は誰に支給される?」)にて詳しく解説しておりますので、よろしければ以下のリンクからご覧ください。
3 夫に対し児童手当の返還を命じた裁判例
前記2のとおり、妻が子どもを連れて別居した場合、夫は児童手当の受給資格を失います。
それにもかかわらず夫が児童手当を受給し続けた場合、受給した児童手当の扱いはどうなるでしょうか?
この点について判断した裁判例として、東京地方裁判所・平成29年11月6日判決が存在します。
3.1 東京地方裁判所・平成29年11月6日判決の事案
裁判例の事案は次のとおりです。
原告である妻と被告である夫は、平成23年3月7日に別居をし、その後、平成25年7月4日に離婚をした夫婦です。
別居の際、妻は子どもを連れて夫の家を出ました。
同居中の児童手当の受給者は夫であり、別居後も、妻ではなく夫が児童手当を受給し続けました。
上記の事情のもと、妻から夫に対し、別居後に夫が受給した児童手当は不当利得にあたり、受給額を妻に返還せよとの請求がなされました。
3.2 判決で示された判断
判決では以下のように述べられ、夫が妻に対し児童手当受給額を返還すべきであるとの判断がなされました。
「児童手当の受給資格者は、「児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は母」であるところ(児童手当法4条1項1号)、被告は、平成23年3月7日に原告が子らを連れて本件マンションを出た後、子らとの交流もなかったものであり、子らの生活について通常必要とされる監督と保護を行っていたとは認められず、子らを「監護」していたとはいえない。そうすると、被告は、子らを監護していたとは認められない同月8日以降の分の児童手当に関しては、その受給資格を有していなかったものと認められ、同日以降、子らを監護し、かつ、子らと生計を同じくしていたと認められる(甲21、乙16、原告本人、被告本人)原告との関係において、上記児童手当相当額を不当に利得したというべきである。」
4 おわりに
児童手当法の規定によれば、東京地方裁判所・平成29年11月6日判決の結論に至ることが適切だと思われます。
別居後に夫が受給した児童手当については、妻からの返還請求が認められるべきでしょう。
しかし、実際に返還請求を行うとなると、交渉の手間や裁判の手間を考えなければなりません。
児童手当の返還を求めるために裁判まで行うことは、費用対効果を考えると決して望ましくはありません。
このようなトラブルを未然に防ぐためには、別居後、できるだけ速やかに児童手当の受給者変更の手続きを講じるべきでしょう。
お問合せはこちら
当事務所では、離婚や男女問題に関する様々なご相談をお受けしています。
ご相談は、仙台市に限らず、全国に対応可能です。
お悩みを抱えている方はお気軽にお問合せください。

記事投稿者プロフィール
下大澤 優 弁護士 仙台弁護士会所属 登録番号49627
専門分野:離婚事件、男女関係事件
経歴:静岡県出身。中央大学法学部法律学科、東北大学法科大学院を経て、平成26年1月に弁護士登録。仙台市内の法律事務所での勤務を経て、平成28年1月、仙台市内に定禅寺通り法律事務所を開設し、現在に至ります。主に離婚事件・男女問題トラブルの解決に取り組んでおります。